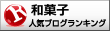忘れているもんですね…
お菓子教室も、会場や人数によって作り方が異なります。近場の予定では、鍋で大福の生地を捏ねることになりました。レンジで作る簡単レシピは、この会場では無理です。 『俺…鍋でもち粉練ったのっていつだっけ…?』と、考えてしまいました。取り敢えず、材料を揃えて昔を思い出しながらもち粉に水を入れて鍋で練ってみました。『こんなもんだろう…』と、いう感覚でよもぎ大福を作ってみたら、腰が抜けたダラダラの生地…。粉も完全に餅状になっていないような気がします。生地に砂糖を入れたのですが、粉にちゃんと熱が入っていないので、翌朝にはボクボクまばらな食感でした。
『くやしい…!』、腕は鈍るものです。感覚も同じです。今の筋力の感覚と昔の筋力の感覚は明らかに違いました。翌日、ゴリゴリに加熱しながら手首が悲鳴を上げるまで練ってみました。出来上がった『大福餅』の食感は、納得できるものになりました。

☝見た目は悪くないのですが、腰が抜けたダラダラの生地になりました。
LA以来だなぁ~
28年前、LAのスーパーさんでお団子を売りました。日本で作った冷凍生地を現地で蒸して、みたらしタレをつけるだけの作業です。消極的な出荷で、あっという間になくなった団子生地。現地のスタッフから『何か出来るか?』と聞かれ、最初は、店頭にある粉で団子を作りましたが、それもあっという間になくなり、もち粉しかありません。何となく、昔家で作った経験をもとに、片手鍋一つで大福餅を作りました。小さな鍋でどれだけもち粉を練ったのか覚えていませんが、その時の経験が今に生きています。工場の機械に粉と水を入れて蒸気をかけるのとはまるで違います。あの時の経験が今生きているとおもえば、全てが繋がっています。装置産業の中にいても、小さな経験が生きているように感じます。

☝シャンとダレない生地になりました。

☝まとめた時の生地が形状を保っているのが大切です。
数社の餅粉を使ってみた
同じお米を使っても、製粉方法によってメーカーごと特徴が変わります。製粉の方法とか、水分量や粒子の細かさなどの要素があります。市販用の小袋の裏に書いてあるレシピは、そのメーカーの粉を使ったレシピですので、粉を変えると全然違ってきます。お菓子教本に書いてあるレシピも、どの粉を使ったか?によって変わって来ます。大きく違うのは、初めに加える水の量と時間。こればかりは、最終的な生地の状態、固さや粘りで見極めるしかありません。今回の大福についても、自分好みの粘りと固さまで練り続けることが美味しさの秘訣でした。
近日中に簡単レシピ公開します!
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
いろんな和菓子のブログが楽しめます
👀のぞいてってください👀
⇩⇩ポチっとね⇩⇩